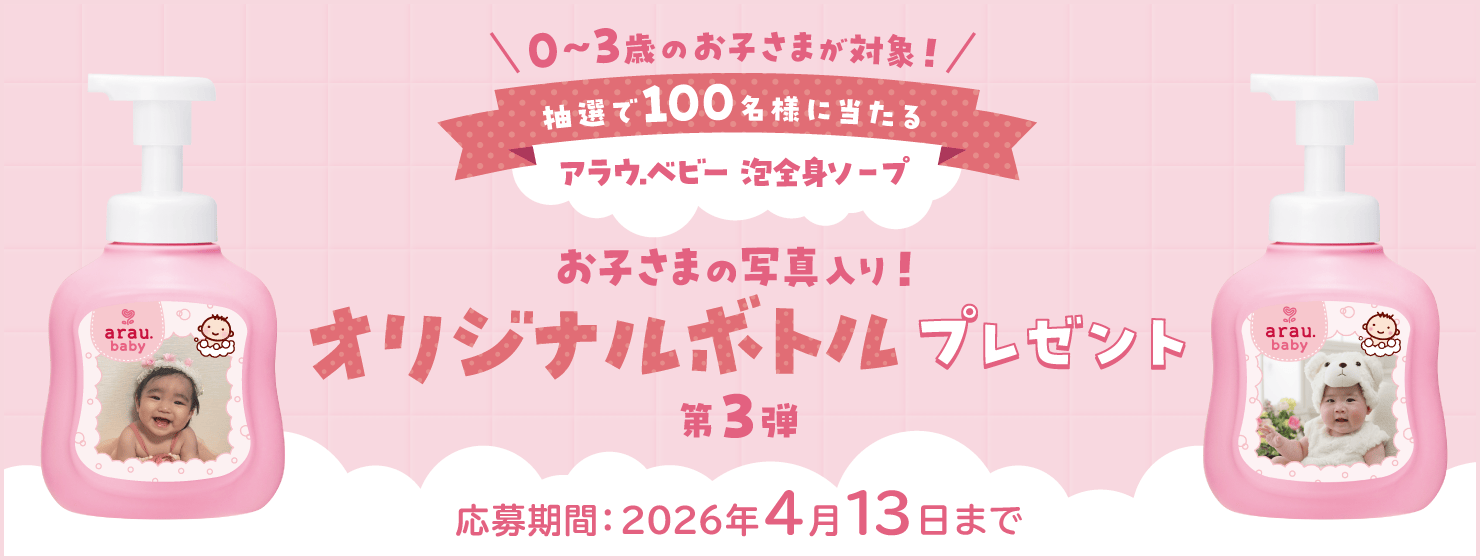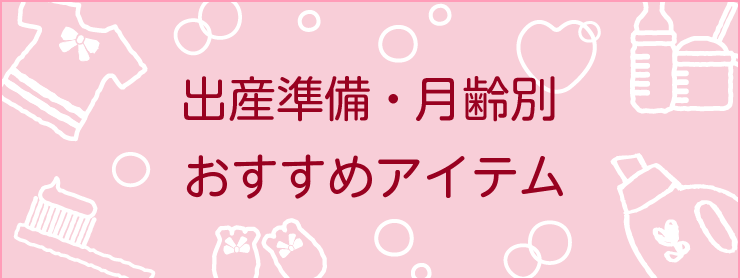赤ちゃんの夜泣きはいつまで続く?泣き止まないときに試してほしいこと

監修:三橋 かな
- プロフィール
-
自身が夜泣きに悩んだ経験から乳幼児睡眠の国際資格を取得。小・中・高校教員免許保持。保育士養成系大学での講師活動や、企業と連携し睡眠講座も開講。instagramを中心に発信を続け、総フォロワー1・6万人。2500人以上の睡眠相談実績を持つ。自身が運営する「るるるん。ねんねサロン」では、毎日夜泣きや離乳食、子育て相談ができる。元アナウンサー。

多くの先輩ママ・パパが「困って大変だった...」と口にする育児のひとつが「夜泣き」です。
授乳しても、おむつ替えをしても、何をしても効果がない。そんな経験のある方も多いはず。泣き止まない赤ちゃんに毎晩何時間も寄り添うのは、ママ・パパにとって負担が大きくつらいものでしょう。
成長に伴っていつかは収まるものとは分かっていても、寝不足でつらい、ストレスが大きい。“今、どうすればよいか”を教えてほしい──。
今回はそんな方に向けて、赤ちゃんの夜泣きの原因や対処法、基本的な知識まで、わかりやすく解説していきます。
「赤ちゃんの夜泣きで睡眠不足…」というママ・パパは多い

楽しみだったはずの育児なのに、「毎晩泣き声を聞き続けて、もう限界...」という方もいるのではないでしょうか。
そもそも「夜泣き」とはどのような状態を指すのか、ここで一度おさらいしてみましょう。
「夜泣き」とは、健康で特に問題のない乳幼児が、夜中に理由もなく泣いて起き、なかなか寝つかない状態をいいます 。
実は、“夜泣き”には医学的な定義がありません。一般的には、生後6か月頃から1歳半頃にかけて、夜間に理由もなく突然泣き出す現象を指します。個人差はありますが、この頃には昼夜の区別もつき始めるため、睡眠リズムが整い、夜間にまとまって寝る子が増える一方、“夜泣き”として頻繁に起きる子も出てきます。つまり、新生児期から体内時計がまだ整わない低月齢の赤ちゃんが「夜に起きて泣く」状態は生理的な現象であり、専門的にいえば「夜泣き」とは区別されます。
けれど、ママやパパにとっては、このような区別はあまり関係ないかもしれませんね。寝る前までは機嫌も悪くなかったのに、「夜中になって急に泣きだし、何をしても泣き止まない」という状態は、ママやパパにとって大変つらいことです。
原因がわからず泣き続けるわが子を前に、困り果ててしまうママやパパは少なくありません。身体的にも精神的にも疲れてしまうのは、当然のことでしょう。
赤ちゃんを健やかに育むためには、ママ・パパの心や体の状態が良好に維持されていることが重要です。夜泣きの時期を少しでも穏やかに過ごすための知識や方法を、次から順にご紹介します。
赤ちゃんの夜泣きの原因

赤ちゃんの夜泣きには、「これが原因」と特定できるものはありませんが、実際には睡眠の発達段階や感覚の敏感さ、不安や不快など、さまざまな要因が重なって起きていると考えられています。
ここでは、赤ちゃんの夜泣きの背景を大きく3つにわけてご紹介します。
●赤ちゃんの夜泣きの原因① 不快なことがあるため
赤ちゃんが夜泣きをするときは、不快なことがあるかもしれません。赤ちゃんは、体の不調や環境の不快感を泣いて伝えます。「泣く」ことは、赤ちゃんにとっては「ことば」であり、不快なことを伝えるサインなのです。
赤ちゃんは免疫力が低く、病気にかかりやすいうえ、適応能力も未熟です 。そのため、体や環境に不快を感じやすく、「お腹が空いた」「おむつが濡れている」「部屋が暑い・寒い」といった不快感が理由で、泣いている可能性があります。
不快感を取り除いてあげると泣き止む場合が多いので、以下のチェックリストを確認し、心地よい状態をつくってあげましょう。
▼赤ちゃんの夜泣きの原因チェックリスト
☐お腹が空いていないか
☐おむつが濡れていないか
☐汗をかいていないか
☐鼻が詰まっていないか
☐寝室が暑すぎたり寒すぎたりしていないか
☐赤ちゃんに衣服やスリーパーなどを着せすぎていないか※1
☐寝室は明るすぎないか
☐周りの音がうるさすぎないか
☐発熱はないか
☐お昼寝がしっかりとれているか
☐眠りにつく前と、寝ついた状態が同じであるか※2
☐おしっこは出ているか
☐便秘になっていないか
☐うんちの色や形状はいつもと同じか
※1 通常、布団は危ないので1歳未満には掛物は必要ないとされています 。代わりに、スリーパーなど着るタイプの寝具を着用させるのが望ましいです。
※2 赤ちゃんが夜中にふと目覚めたとき、寝ついたときと環境が違うことに驚き、泣くことがあります 。「布団の上で寝かしつける」ようにすることで、目覚めたときでも、赤ちゃんがすんなりと再入眠しやすくなります。
特に「お腹が空いている」は新生児期(生後28日未満)によくある夜泣きの原因です。新生児の赤ちゃんは、母乳やミルクを一度に飲める量が少ないため、お腹が空くと、そのたびに泣くことも。この場合は、満腹になれば、落ち着いて眠ってくれることが多いようです。
また、もしも体温が高い、呼吸が荒いなど、いつもと違う様子がある場合は、かかりつけ医や、#8000(こども医療電話相談)などに相談しましょう。
チェックリストを満たしても、なかなか寝ない、夜泣きがおさまらないような場合は、「自分で寝る力」をつけるために、乳幼児睡眠コンサルタントに相談するのも一案です。
●赤ちゃんの夜泣きの原因② 体内時計や睡眠サイクルが未発達なため
夜泣きとは少し異なりますが、赤ちゃんが夜間に頻繁に泣いて起きる理由のひとつに、体内時計や睡眠サイクルの未熟さがあります。
生後2~3か月ごろまでは、昼夜の区別がついていないことも多く、睡眠の大半が浅いレム睡眠であるため、ちょっとした刺激で目覚めやすいのです。このため、まだ「夜泣き」とは呼べない時期でも、夜間に何度も泣き起きる状態が続くことがあります。
【出典】「未就学児の睡眠指針」(厚生労働省)
●赤ちゃんの夜泣きの原因③ 記憶や情報の整理のため
赤ちゃんの夜泣きの原因には、記憶や情報の整理が関連しているケースもあります。
大人と同様、赤ちゃんもその日にあったことを脳内で記憶として定着させます。特に生後4~5か月頃は、人や表情の区別・認識ができるようになり、赤ちゃんが周囲の刺激にも敏感になってくる時期です。
しかし、日中の刺激が多すぎたり強すぎたりすると、情報整理や処理が追いつかず、眠りが不安定になって短時間の浅い眠り/覚醒を引き起こしたりすることがあります。
赤ちゃんの夜泣きはいつまで?乗り越えるために知っておきたいこと

夜泣きが続いて心配なのは、そばで寄り添うママ・パパへの影響です。
夜泣きに限らず、赤ちゃんが泣くことでイライラしてしまうのは、当然のことです。ママやパパは、自分を責める必要はありません。赤ちゃんは泣くのが仕事、当たり前のことなのです。赤ちゃんが泣いても、誰が悪いわけではないのです。
ここでは、赤ちゃんの夜泣きについて、始まりやピーク、乗り越えるための心構えを紹介します。
●赤ちゃんの夜泣きには個人差がある
赤ちゃんの夜泣きは、早いと生後3か月頃から始まります。しかし、すべての赤ちゃんに夜泣きがあるわけではなく、「まったくなかった」というお子さんもいます。
夜泣きは時間帯も続く期間も、赤ちゃんによってさまざまで、個人差が大きいのが特徴です。
●赤ちゃんの夜泣きのピークは生後7~9か月頃
赤ちゃんは生後3~4か月頃から昼夜の区別がついてきて、少しずつまとまって寝られるようになってきます。
新生児期は、短い間隔で「寝て起きて」を繰り返すのが特徴でしたが、3~4か月を過ぎると、「夜に眠っている時間」が自然と長くまとまってくるようになるのです。
赤ちゃんの夜泣きのピークは、生後7~9か月頃だといわれます 。1歳を過ぎると穏やかになり、成長にともない、3歳になる頃には落ち着いてくる子が多いようです(ただし個人差はあります)。
●赤ちゃんのお世話をするママやパパがリラックスすることも大切
夜泣きのたびに、プレッシャーを感じる方もいるでしょう。しかし、その緊張感は赤ちゃんに伝わってしまうことがあります。
夜泣きとうまく付き合うためには、「赤ちゃんのお世話をするママやパパがリラックスすること」、「夜泣きは悪いことではないと理解すること」がポイントです。赤ちゃんは、何をしても泣き止まないこともあります。
リフレッシュする時間をつくったり、周囲に助けを求めたりするためにも、
・おじいちゃんおばあちゃんにお世話を代わってもらう
・友だちに話を聞いてもらう
・子育ての相談窓口に電話をする(子育て支援センターなど)
──などの対処方法で、気持ちを吐き出して気分転換できるタイミングを設け、くれぐれも1人で悩まないようにしてください。
睡眠の成長段階にある「夜泣き」は、赤ちゃん自身が「何とかして自分を落ち着かせなきゃ」と練習している時間でもあります。お子さんの“セルフねんね”のチャンスを奪わないためにも、ママたちが「〇〇して眠らせなきゃ」と思い込みすぎないようにしましょう。
【出典】「赤ちゃんが泣きやまない 泣きへの理解と対処のために」(厚生労働省)
赤ちゃんの夜泣きをできるだけ減らすための対処法

ここからは、赤ちゃんの夜泣きを減らすための、具体的な方法を見ていきましょう。
夜中に突然泣き出したときの対処法だけでなく、そもそも「夜泣きする状況」をつくらないようにするための対策も重要です。
いつの時代も、ママ・パパたちは試行錯誤しながら赤ちゃんの夜泣きを乗り越えてきました。夜泣きのピーク時期に備えて、お子さんにあった夜泣きの対処法を見つけてみてくださいね。
●対処法① リラックスできる音を聴かせてあげる
ママのお腹の中で聴いていた音を聞くと、赤ちゃんは“あの頃の安心感”を思い出して、すーっと落ち着くことがあります。
おすすめは、ママやパパの声や歌、ママが妊娠中によく聴いていた音楽や、胎内の音に似ているとされるホワイトノイズ(テレビの砂嵐の音や、ビニール袋をすり合わせた音など)も、赤ちゃんが落ち着きやすいといわれます。最近ではスマートフォンのアプリやホワイトノイズマシンなども活用できるので、試してみるのもよいでしょう。
ただし注意点として、機器やスマートフォンから赤ちゃんの耳をしっかりと離してあげてください。
●対処法② おくるみやスワドルで包んであげる
おくるみやスワドルの活用も、夜泣きの対処法になります。胎内で小さく丸まっていた姿勢に近い状態になることで、赤ちゃんが安心して眠りやすくなるのです。ママの胎内環境を再現してあげることは、有効な夜泣き対策だといえます。
さらに、おくるみは、赤ちゃんが両手や両足をビクッと動かしてしまう「モロー反射」が原因の夜泣きにも効果的です。おくるみで包んであげることで、動いた手足に赤ちゃん自身が驚き、目覚めてしまうのを防げます 。
赤ちゃんが眠りについてしばらくたったら、様子を見ながらおくるみを少しずつゆるめてあげたり、状況に応じて外してあげると、体が熱くなりすぎたり、動きが制限されすぎるのを防ぐことができます。眠ってからも赤ちゃんの表情や手足の動きに目を向けて、心地よく過ごせるように調整してあげることが大切です。
なお、おくるみやスワドルのかわりに便利なバスタオルを使いたくなるかもしれませんが、思った以上に暑くなったり、タオルが顔にかかってしまったりとリスクがあるので避けましょう。
おくるみやスワドルの卒業時期は、赤ちゃんの動きが活発になり寝返りを始める生後3~4か月頃が目安になります。
●対処法③ 抱っこして赤ちゃんの背中を優しくトントンしてあげる
夜中に赤ちゃんが目覚めて泣き出したら、赤ちゃんの背中をトントンしたり、さすったりしてみてください。ママやパパが近くにいることがわかると、安心して寝つきやすくなることがあります。
ただし、窒息などの事故の可能性もあるため、添い寝はせず、親と子は別の寝床で寝ましょう 。
消費者庁・国民生活センターは、就寝時の子どもの窒息事故の危険を指摘し、「安全な寝床に赤ちゃんを一人で寝かせる」ことを推奨しています。ご家庭の事情や住宅事情にあわせて対応してください。
【参考】「Vol.570 就寝時の子どもの窒息事故に注意しましょう。ベビーベッドを利用することで避けられる事故があります。」(消費者庁)
●対処法④ 安全で快適な睡眠環境をつくる
赤ちゃんにとって心地よい睡眠環境をつくってあげることも、夜泣きには有効です。室温は赤ちゃんにとって適温ですか?また、明るすぎたり、うるさすぎたりしませんか?
赤ちゃんは環境への適応能力が未熟なため、寝室の環境が快適でないと、夜泣きにつながったり、眠りにつきにくくなったりすることがあります。また、いったん目が覚めたあとも、再び眠りに戻るのが難しくなることも。
新生児期~乳児期は身体のさまざまな機能が発達していく大事な時期でもあるため 、安全な環境づくりに配慮しましょう。
室温や照明、音や寝具など、赤ちゃんに適した室温の管理については以下の関連記事で詳しく紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
- 合わせて読みたい
- 赤ちゃんの部屋の温度・湿度の目安は?暑さや寒さを感じているサイン
●対処法⑤ しっかりとお昼寝をとる(指標は活動時間表)
お昼寝は、赤ちゃんが夜スムーズに眠りにつくために大切な役割を果たします。
特に、活動時間に合わせて適切にお昼寝をとることで、過度な疲れや興奮を防ぎ、夜の寝つきがよくなることがあります。反対に、お昼寝が長すぎたり遅すぎたりすると、夜の寝つきが悪くなることもあります。赤ちゃんの月齢に合った活動時間の目安を参考に、昼寝のタイミングを整えてみましょう。
【月齢別の活動時間の目安】
| 月齢 | 活動時間の目安(1回) |
|---|---|
| 0〜1か月 | ~約40分 |
| 1〜2か月 | 約40分~1時間 |
| 2〜3か月 | 約1時間~1時間20分 |
| 4〜5か月 | 約1時間20分~1時間30分 |
| 6〜8か月 | 約2時間~2時間30分 |
| 9か月 | 約2時間30分~3時間 |
| 10か月~1歳2か月 | 約3時間30分~4時間 |
| 1歳3か月~1歳6か月 | 約4時間~6時間 |
| 1歳6か月~3歳 | 約6時間 |
表を見ると、赤ちゃんが起きていられる時間は、意外と短いことがわかります。
お子さんの活動量や状態に合わせることが前提ですが、上記を参考に寝かしつけのタイミングを見て寝かせてみましょう。
●対処法⑥ 日光を浴び、身体を動かす(日中)
お天気のよい日には、日中に外に出て日光を浴びたり、お散歩したりして、生活リズムを整えてあげましょう。
生後3〜4か月頃からは昼と夜の区別がつきやすくなってきます。この時期から「朝は明るく、夜は静かに暗く」といった生活リズムを意識することが、夜の眠りを安定させる助けになります。
特に、お子さんと同じ部屋で寝ているご家庭では、大人の就寝時刻やテレビ・スマホの使用時間などが赤ちゃんのリズムに影響することもあります。家族みんなで「早寝・早起き」の習慣を意識することや、日中疲れすぎないように適度にお昼寝をとることが夜泣き対策のひとつになります。
●対処法⑦ 日中、十分なスキンシップをとる
赤ちゃんとのスキンシップは、親子の愛着形成をはかる大切な時間です。ママ・パパがスキンシップをとってあげると、赤ちゃんは「近くにいるんだ」と安心して、眠りにつきやすくなります。
赤ちゃんとゆったりとリラックスして触れ合うことは、ママ・パパ自身が気持ちのゆとりを持つことにもつながるでしょう。
●対処法⑧ ねんねに向けたルーティンをつくる
夜泣きの対処法のひとつとして、ねんねルーティンをつくることはとても大事です。
寝る前に毎日同じような行動をすることで、赤ちゃんに「これから寝るんだ」と自然と体で覚えさせることができます。
たとえば「授乳や食事→お風呂」の流れをパターン化し、就寝前は「子守唄をうたう」「絵本を読む」といった入眠儀式を行うことで、赤ちゃんの眠る準備が整いやすくなります。
寝かしつけに苦労することが多い方は、赤ちゃんの「生活リズムを整える」ためにも、ねんねルーティンを取り入れてみましょう。寝かしつけのコツについては、以下の記事も参考にしてください。
- 合わせて読みたい
- 【年齢別】赤ちゃんを寝かしつけるコツ|よい睡眠で健やかな成長を
夜泣きは赤ちゃんの成長過程のひとつです
夜泣きは、子育てにおいてママ・パパが抱えやすい悩みのひとつです。
夜泣きに対応するあいだは眠れないだけでなく、愛するわが子を前に「どうしたのかな」「つらいのかな」と不安な気持ちになってしまうものでしょう。
しかし、赤ちゃんが夜に泣くことも、泣き止ませられないことも、決してママやパパの責任ではありません。赤ちゃんは疲れたり、飽きてしまったり、理由もなく泣いたりすることもあります。
夜泣きは経験するかしないかをはじめ、期間や頻度・回数など、赤ちゃんの個人差が大きいのが特徴です。実際に「まったく夜泣きがなかった」という赤ちゃんもいれば、「1歳を過ぎてもよく泣いていた」という子もいます。
夜泣きは、赤ちゃんの睡眠リズムや情緒が発達していく中で、見られやすい変化のひとつです。夜泣きが続くと不安になるものですが、それもまた赤ちゃんが少しずつ眠りのリズムを身につけていく過程なのかもしれません。
心身共に大変な時期ですが、泣いてもいい、泣き止まなくても大丈夫。泣いているその声もまた、「生きている証」。こんな心持ちで、完璧に乗り越えようとせず、少しずつ、気長に付き合っていけるとよいですね。