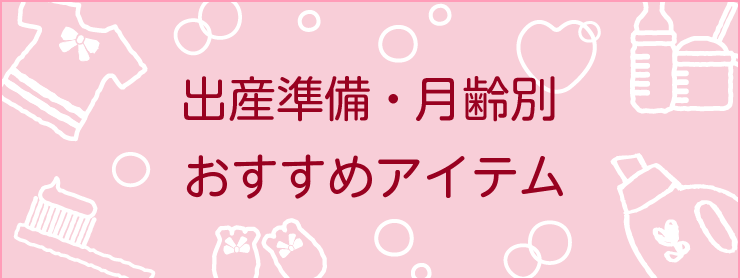赤ちゃんが寝ないのはなぜ?全然寝てくれない理由や寝かしつけのコツ

監修:三橋 かな
- プロフィール
-
自身が夜泣きに悩んだ経験から乳幼児睡眠の国際資格を取得。小・中・高校教員免許保持。保育士養成系大学での講師活動や、企業と連携し睡眠講座も開講。instagramを中心に発信を続け、総フォロワー1・6万人。2500人以上の睡眠相談実績を持つ。自身が運営する「るるるん。ねんねサロン」では、毎日夜泣きや離乳食、子育て相談ができる。元アナウンサー。

可愛い赤ちゃんですが、自分自身が疲れて大変なときに寝てくれないと「早く寝てくれないかな…寝たいのはこっちなのに…」などと思ってしまうでしょう。
「日中やらなければいけないことがたくさんあるのに寝てくれない」
「へとへとになってようやく横になれたところで赤ちゃんが何度も起きる」
なかなか寝ない赤ちゃんを無理に寝かせようとしても難しいもの。
今回の記事では、赤ちゃんが寝ない理由や寝かしつけに効果的な対策を紹介します。お子さんに合う方法を見つけて上手に工夫すれば、スムーズに寝てくれるかもしれません。
赤ちゃんがなかなか寝ないことはママ・パパのよくある悩み
冒頭に書いたように、赤ちゃんが寝てくれないことは、子育てでよくある悩みの一つです。
たとえば赤ちゃんが昼間だけでなく、夜中も寝ないと、ママやパパが睡眠不足になってしまいます。日中の活動にも影響を与え、疲労も溜まるでしょう。
また、あまりに寝てくれない場合、発達に影響はないか、脳や身体に何か問題があるのか、病気ではないかなどと、心配になってしまいます。
悩みや不安を緩和するためにも、赤ちゃんがうまく眠れるようにサポートする方法を知っておくとよいでしょう。赤ちゃんが寝ないとき、“ママやパパが頑張りすぎないこと”は大切。でも同じくらい、“赤ちゃんが眠れるように手助けする方法”を知っておくことも、大きな支えになります。
赤ちゃんが寝ない主な理由って?

赤ちゃんが寝ない理由には、生理的な不快感、心理的な不安などのほか、脳や体の成長・発達に関連した要因があります。
具体的な理由の説明に移る前に、ひと口に「赤ちゃん」といっても、生後28日までの新生児、生後1年未満までの乳児で睡眠パターンが異なります(ただし個人差があります)。以下の表では一般的に言われている新生児と乳児の睡眠パターンの特徴をまとめました。
●赤ちゃんの睡眠パターン
| 新生児
(生後28日まで) |
・睡眠時間はおおよそ15~20時間 ・半眠半醒の状態で短時間の睡眠と覚醒を繰り返す ・1日単位の睡眠・覚醒リズムははっきりしない ・刺激で睡眠・覚醒リズムが乱れやすい
|
|---|---|
| 乳児
(生後1年未満) |
・睡眠時間はおおよそ12~16時間 ・睡眠・覚醒リズムが徐々に24時間サイクルになってくる ・生後1か月頃から3~4時間ごとに睡眠と覚醒を繰り返す ・生後2~3か月頃から日中は長く覚醒し夜に長く眠る「昼夜の区別」がつくようになる ・夜泣きが見られる(生後6か月頃からが多い)
|
表に挙げた月齢や時期による違いを踏まえたうえで、「赤ちゃんが寝ない理由」を詳しく解説します。
●寝ない理由① お腹が空いているため
赤ちゃんは、一度に飲める母乳やミルクの量が限られているため、すぐにお腹が空いて目が覚めやすくなります。特に新生児は胃が小さく、おっぱいを吸う力も弱いほか、ママの母乳も最初は多く出ないといった理由が重なり、お腹が空きやすくなるのです。
生後2か月~3か月になって、一度に飲める量が多くなると、ある程度まとめて眠ってくれるようになるケースが多いです。
●寝ない理由② 環境や身体に不快なことがあるため
赤ちゃんは生理的な不快を感じると、泣いて訴えることがあります。
▼よくある赤ちゃんの不快の原因
・おむつが濡れている
・ゲップが出ていない
・暑い・寒い
・周りの音がうるさい
・光がまぶしい
・あせもができてかゆい
・肌がチクチクする
・おなかがいっぱいで苦しい など
このような不快の原因を取り除いてあげると、よく寝てくれることがあります。
●寝ない理由③ 睡眠のサイクルが大人と違うため
一般的に赤ちゃんは、一度に長時間眠ることは少なく、特に新生児の間は2~3時間おきに目を覚まします。3時間ごとの授乳が確立すると睡眠と覚醒のリズムが徐々に安定し、生後2~3か月経ってようやく昼夜の区別ができ始めます。そうして徐々に夜長時間眠るようになっていくのです。
また、赤ちゃんは、レム睡眠(浅い睡眠)とノンレム睡眠(深い睡眠)のサイクルが不規則で短いです。特に生後3~4か月くらいまでは総睡眠時間の半分程度が浅い眠りであるレム睡眠になるため、刺激に敏感に反応してしまい、目を覚ましてしまいます。
●寝ない理由④ 体内時計が整っていないた
前述のとおり昼間と夜間の区別がつき始めるのは生後2~3か月後のため、新生児期には昼夜の区別がありません。このように、体内時計が整っていないこともなかなか寝ない理由の一つでしょう。
月齢が進むにつれて、体内時計や神経系の発達により睡眠リズムが整い、夜間にまとまって眠れるようになっていきます。 また、授乳の間隔が徐々に空いてくることで、夜に空腹で起きる回数が減り、より長く眠れるようになるのです。
●寝ない理由⑤ 寝たり起きたりを繰り返すことが発達に必要なため
赤ちゃんは、成長ホルモンが分泌される深い眠りと、刺激に反応して目覚める浅い眠りを繰り返すことで、脳や情緒の発達、環境への適応力を育てています。寝たり起きたりは、乱れではなく自然な発達のプロセスです。
なかなか寝ない赤ちゃんを寝かしつけるコツ

赤ちゃんがなかなか寝ないのは、成長の段階として必要だということはわかりました。ですが、ママやパパのためにも寝かしつけのポイントは知りたいものです。
対処法としては、まずは赤ちゃんが不快を感じにくい環境調整が必要になります。また、赤ちゃんを安心させることも寝かしつけのコツです。以下で詳しく解説していきます。
●赤ちゃんの寝室の環境を整える
寝かしつける部屋の室温や湿度を適切に保ち、睡眠環境を整えましょう。寒すぎ、暑すぎに要注意です。
▼赤ちゃんが快適な睡眠環境
・夏:26℃~28℃、冬:20℃~23℃
・湿度:40%~60%(季節は問わない)
ただし、数字はあくまで目安です。秋冬などは大人が少し肌寒いと感じるくらいが赤ちゃんにとって快適に寝られる環境になります。
寝室はカーテンを閉じて暗くし、騒音を避けてできるだけ安心できる環境に保ちます。夜中の授乳も部屋が暗いまま行うとよいでしょう。
どうしても明るくしなければならないときは、足元などで明かりをつけるようにします。暖色系の薄暗い明かりにして、赤ちゃんの目に光が入らない位置でつけましょう。
夜に天井の照明の明かりを切り替えて豆電球にし、薄暗さを保つ方もいますが、赤ちゃんがまぶしく感じるため、天井の照明はつけずに寝かせてあげましょう。
赤ちゃんに適した温度・湿度の目安については、次の記事で詳しく紹介しています。参考にしてください。
- 合わせて読みたい
- 赤ちゃんの部屋の温度・湿度の目安は?暑さや寒さを感じているサイン
また、寝具を清潔に保つことも重要です。通気性や吸水性に優れて肌ざわりのよい寝具を使い、定期的に洗濯しましょう。なお、赤ちゃんの衣類を洗濯する際は、肌への刺激や吸水性の低下につながるため、なるべく柔軟剤を使わないことをおすすめします。
●リラックスできる音を聞かせる
ママやパパの声や歌、ママが妊娠中によく聴いていた音楽、胎内の音に似たホワイトノイズなどを聞くと、赤ちゃんが落ち着いて寝入ってくれることがあります。
ホワイトノイズは、ノイズ(雑音)の一種です。換気扇やテレビの砂嵐のような「サーッ」「シーッ」「ゴーッ」といった音で、リラックス効果・安眠効果があるとされています。音楽アプリなどで検索すると、睡眠用のホワイトノイズが多く配信されています。
ただし、赤ちゃんに音を聞かせる際にスマートフォンやタブレットを使う場合、強い光や大きな音を赤ちゃんに浴びせないように注意してください。また、画面のブルーライトは睡眠リズムを乱す可能性があるため、赤ちゃんに画面を見せない工夫も必要です。
●赤ちゃんと寝る前にスキンシップをする
赤ちゃんは、不安や不快を感じると、なかなか眠りにつけないことがあります。特に新生児期は、まだ目がはっきり見えておらず、周囲の様子を視覚で確認することができません。そのため、抱っこや肌のぬくもり、声のトーンなど、スキンシップによって安心感を得ることがとても大切です。
抱っこしたり、子守歌を歌ったり、背中をトントンしたり、お腹に優しく触れたりすると、ママやパパが近くにいることがわかって安心し、寝つきやすくなることがあります。
ただし、窒息などの事故を防ぐために、大人と同じ布団やベッドで赤ちゃんを寝かせるのは避けましょう。消費者庁より窒息事故についての注意喚起がなされているので、ぜひ確認してください。
【参考】「Vol.570 就寝時の子どもの窒息事故に注意しましょう。ベビーベッドを利用することで避けられる事故があります。」(消費者庁)
●毎日同じ寝かしつけ方をする
赤ちゃんの寝る時間を決めて、毎日同じ方法で眠らせることも安心感につながります。ルーティン化することで、赤ちゃんが「いつもと同じ」と感じて安心するためです。
昼夜のリズムができた生後2~3か月頃からは、就寝時間や起床時間を徐々に一定にしていき、夕方あたりから寝かしつけの流れを決めておくと、生活リズムができて眠りやすくなります。
●おくるみで包んであげる
赤ちゃんが安心しやすい方法に「抱っこ」があります。昔は「抱き癖」をつけないようにあまり抱っこしないほうがよいという考え方もありましたが、現在は赤ちゃんの「抱っこしてほしい」というニーズに応えてあげることが重視されています。
抱っこのような安心感を赤ちゃんに与えてくれるのが「おくるみ」です。やわらかい布に包まれる温かさと心地よさが、赤ちゃんを安心させ、眠りへといざなってくれます。また、新生児期から生後4か月頃までに見られるモロー反射(音や刺激に反応して手足を大きく動かす反射)によって目が覚めてしまうのを、おくるみでやさしく包むことで抑え、よりスムーズな眠りをサポートします。
ただし、おくるみを使うときは、温度調節に気をつけてください。
●日光を浴びる
午前中に太陽の光を浴びると、眠気を促すホルモン「メラトニン」の材料となるセロトニンの分泌が盛んになります。また、体内時計を整えて昼夜のリズムをつくってあげるためにも、日光は重要な役割を果たすので、生後3か月を過ぎれば散歩なども効果的です。
●眠たいサインをチェックする
寝かしつけのベストなタイミングを知っておくと、スムーズに寝入ってくれるかもしれません。あくびは眠たいサインと思うかもしれませんが、疲れのサインである可能性もあります。疲れすぎると赤ちゃんは逆に興奮状態になり、寝てくれないことが多いです。
タイミングよく寝かしつけをするためには、赤ちゃんの様子をよく観察して眠たいサインをチェックしましょう。
代表的な眠たいサインの例には以下があります。
▼眠たいサイン
・あくびをする(疲れすぎの可能性もあり)
・ぼーっとした表情をする
・顔をこする、目をこするしぐさをする
・ぐずる・泣く
・おもちゃに興味を示さない
・のけぞる
・耳をひっぱる
ただし、眠たいサインが出た時点で、すでに疲れすぎていることもあります。その場合、ぐずってなかなか寝てくれなかったり、寝てもすぐに目を覚ましたりすることがあります。
サインを見てから寝かしつけてもうまくいかないと感じる場合は、月齢に応じた「活動時間」(起きていられる時間の目安)を参考に、少し早めに寝かしつけを始める方法もおすすめです。
●赤ちゃんの寝かしつけのタイミングをチェックする
赤ちゃんが一度に「ご機嫌で起きていられる時間」(活動時間)は限られています。
月齢別に活動時間の目安を示すと以下の通りです。
| 月齢 | 活動時間 |
|---|---|
| 生後1か月未満 | 40分未満 |
| 生後1~2か月 | 約40分~1時間 |
| 生後2~3か月 | 約1時間~1時間20分 |
| 生後4~5か月 | 約1時間20分~1時間30分 |
| 生後6~8か月 | 約2時間~2時間30分 |
| 生後9か月 | 約2時間30分~3時間 |
| 生後10か月~1歳2か月 | 約3時間30分~4時間 |
※IPHI妊婦と乳幼児睡眠コンサルタント資料より作成
活動時間を過ぎたあたりが寝かしつけのタイミングになりますが、時間が大きく過ぎたり活動量が多すぎたりすると、疲れすぎて逆に寝られなくなることがあるのでご注意ください。
- 合わせて読みたい
- 【年齢別】赤ちゃんを寝かしつけるコツ|よい睡眠で健やかな成長を
赤ちゃんが寝ない理由を知って適切な対応を
赤ちゃんがなかなか寝てくれないのは、実は「よくあること」。特に月齢が浅い時期は、「半分眠っていて、半分起きているような状態(半眠半醒)」が続くため、ちょっとした刺激ですぐ目が覚めてしまうのは自然なことです。
まずは、赤ちゃんの月齢ごとの睡眠の特徴を知ることが第一歩になります。
また、空腹や暑すぎ・寒すぎ、まぶしさ、着心地の悪さなど、ちょっとした不快も眠りを妨げる原因になります。室温や湿度、音や光の環境を整え、赤ちゃんがリラックスできる心地よさをつくってあげましょう。肌着や寝具など、触れるもののやさしさも意外と大切です。 そのうえで、赤ちゃんが眠たくなりそうなタイミングを見はからって、抱っこやスキンシップ、心地よい音やおくるみなど、紹介した寝かしつけのコツを試してみてください。
育児は毎日の積み重ね。ママやパパ自身が無理をせず、赤ちゃんの眠りのリズムが少しずつ整っていく中で、休める時間を上手にとっていくことが大切です。そして、赤ちゃんと一緒に、心にゆとりのある時間が増えていきますように。