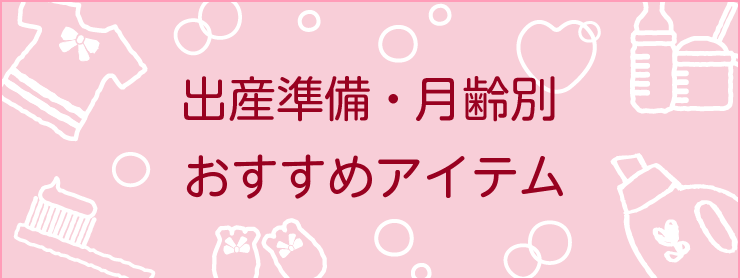ほ乳びん拒否で試してほしい7つの対処法|克服方法は焦らず探そう

監修:古市 菜緒
- プロフィール
-
助産師としてこれまで10,000件以上の出産に携わり、5,000人以上の方を対象に産前・産後セミナー等の講師を務める。助産師のレベルが世界的に高いAUSとNZで数年生活、帰国後バースコンサルタントを起ち上げる。現在は、高齢出産の対象であるOVER35の方にむけた「妊娠・出産・育児」をサポートする活動を行う。その他、関連する記事の執筆やサービス・商品の監修、企業のセミナー講師、産科病院のコンサルタントなどを務める。

「赤ちゃんがほ乳びんでミルクを飲んでくれない…」
「今までほ乳びんで飲んでくれていたのに、急に嫌がるようになった…」
職場復帰の予定があったり医師から母乳不足や栄養不足を指摘されたりして「ほ乳びん授乳」が必要なのに、「赤ちゃんが飲んでくれない…」と悩むママは多いです。
母乳は飲むにもかかわらず、ほ乳びんで飲むのを嫌がる現象を「ほ乳びん拒否」とよびます。赤ちゃんには一般的によくみられる現象で、乳首の素材・サイズ、ミルクの味など原因はさまざまです。赤ちゃんは変化に敏感なため、何かしらの違和感をいだくと、ほ乳びんを嫌がってしまうのです。
本記事では、ほ乳びん拒否のとらえ方、主な原因と対策、試してほしい対処法について紹介します。
ほ乳びん拒否は克服させるべき?

ほ乳びん拒否は、栄養状態などに問題がなければ「母乳だけで満足している」サインです。赤ちゃんの月齢や成長ぐあい、育児の環境によっては必ずしも克服すべきものではありません。
たとえば、
①母乳をしっかり飲んでいて体重の増え方に問題がない
②母乳をしっかり飲んでいて便・尿の回数が月齢の基準を満たしている月齢が3か月~4か月でもうすぐ離乳食が始まる
③完全母乳でもママの負担が少ない
などの状況であれば、ほ乳びん拒否を無理に克服する必要はなく、母乳育児を続けるのも選択肢の一つです。
一方、産後すぐで母乳の出が悪い、赤ちゃんの体重増加の不足で医師や助産師から混合栄養(母乳の不足を人工ミルクで補う栄養法)を指導された、保育園に預ける予定が決まっている、夜中の授乳を家族で分担したい、ほ乳びんで授乳できると育児が楽になるといった場合には、ほ乳びん拒否の克服が必要になります。
対策や対処法はいくつもあるため、克服に向けて試行錯誤していきましょう。
ほ乳びん拒否が起こる主な理由と対策
「7つの対処法」に進む前に、ほ乳びんを拒否する場合に考えられる3つの主な理由と、それぞれの対策を紹介します。
前述のとおり、ほ乳びん拒否は赤ちゃんが「何かしらの違和感」をいだいて起こるケースが多く、(1)ミルクの温度、(2)ミルクの味、(3)ほ乳びんの乳首への違和感が三大原因にあげられます。
ミルクの温度以外は、対策にある程度のコストが必要になるため、次に説明する「7つの対処方法」から試していただいてもよいでしょう。
【理由1】ミルクの温度が気に入らない
ミルクが熱すぎたり、冷たすぎたりすると、ほ乳びんを嫌がる場合があります。
◎対策
赤ちゃんが好むミルクの温度は、母乳と同じ人肌ぐらいの温度です。しかし、冬場や哺乳瓶の素材、ミルクの量によっては、作ってもすぐ冷えてしまう場合があります。また、飲むスピードが遅い場合も、時間が経つにつれミルクが冷えてしまうため、途中で飲むのを嫌がることがあります。
そのほかにも、人肌だと思って作ったミルクが、赤ちゃんにとって熱すぎる場合もあります。
ミルクの温度を見るときは、冷えがちな手先でみるのではなく、腕の内側にミルクを垂らし温度を見る方法がより確実です。そして授乳しながらも適宜ミルクの温度を確認するとよいでしょう。
【理由2】ミルクの味が苦手
赤ちゃんは生後1か月~3か月ころから味がわかるようになり、好みも生じます。お使いのミルクの味が嫌いで拒否するケースもあるでしょう。また、ミルクそのものの味以外にも、粉ミルクを溶かすお湯の味を嫌がる場合もあります。
◎対策
別のメーカーの商品を試してみましょう。購入せずに、まずは試供品を試してみるのがおすすめです。粉ミルクだけでなく液体ミルクも検討してみるとよいでしょう。商品を変えるほかに、濃度を少し調整するのも手です。
人工ミルクはダメでも搾乳なら飲む場合があります。搾乳が飲めれば、冷凍した搾乳を保育園に持参して預ける方法も可能です。
粉ミルクを溶かすお湯についても、一度煮沸させた湯を冷まして使ってみたり市販のベビー用ピュアウォーターなどを試してみたりするのもよいでしょう。
【理由3】ほ乳びんの乳首が飲みにくい
ほ乳びんの乳首を嫌がるケースもあります。「感触が嫌い」「飲みにくい」「サイズが合わない」などの原因が考えられます。また、母乳とゴム乳首では、授乳時の赤ちゃんの口の動きが違うため、乳首が違うことによる乳頭混乱を起していることも原因のひとつです。
◎対策
月齢に合うサイズや形状の乳首、別メーカーの乳首を試してみます。
乳首は大きさだけでなく、吸う力の成長に合わせて吸い口の穴の形も異なるため、月齢に合うものに変えるだけで飲むケースもあります(表参照)。また、乳首の素材もいくつか種類があり、別素材を試してみてもよいでしょう(表参照)。乳首が古く劣化して飲みにくい場合は、新品に変えると飲むケースがあります。
母乳授乳メインだった赤ちゃんがほ乳びんを使用する際は、母乳に近い口の動きでミルクが出る乳首もあるため、検討してみるとよいでしょう。
【乳首の穴の形】
●丸穴:吸う力の弱い新生児向け。
●クロスカット:穴がXの形の切り込みになっており、吸う力によって飲めるミルクの量が変わるタイプ。赤ちゃんの飲みたい欲求が強いほど多く飲める。
●スリーカット:穴がYの形の切り込みになっており、クロスカットに比べて一度に出る量が限られてむせにくい。
【乳首の素材の種類】
●シリコンゴム:ゴム特有のにおいがなく、赤ちゃんが抵抗なく口にしやすいが、ややかたい。
●天然ゴム:ゴム特有のにおいがあるが、やわらかく、本物の乳首に近い感触
●イソプレンゴム:天然ゴムに近い質感で、ゴム臭がない。
ほ乳びん拒否が治らないときに試してほしい7つの対処法

先ほど赤ちゃんがほ乳びんを嫌がる主な原因を3つあげ、それぞれ対策を紹介しましたが、実際のところ少しの工夫や環境の変化で、ほ乳びん拒否が克服できるケースも多くあります。なかには飲ませる姿勢を変えたり、時期を少し空けたりしただけで、ほ乳びんを嫌がらなくなった例もあるほどです。
ミルクや乳首を変える前、変えた後にも簡単に試せる「7つの対処法」を紹介します。複数の対策や対処法などを組み合わせて、いろいろと試行錯誤してみてください。
【対処法1】お腹が空いているときに飲ませる
対処法のなかでは最も簡便な方法です。母乳を与えるのを少しがまんして、赤ちゃんが空腹を強く訴える状態になってから、ほ乳びんを与えてみます。空腹の程度が強ければ多少の違和感があってもほ乳びんから飲むケースがあり、何度か繰り返せばしだいにほ乳びんに対する抵抗感が薄れるでしょう。
【対処法2】ミルクをあげる人を変える
ママ以外の人があげると、ほ乳びんで飲むことがあります。赤ちゃんがママを「おっぱいをくれる人」と認識しているため、ママがそばにいると母乳を欲しがってしまうと考えられています。また、環境を変えると気分が変わるのも理由の一つかもしれません。空腹時に試すと、さらに効果的です。
【対処法3】さりげなくおっぱいからほ乳びんにすり替える
まずおっぱいをあげ、途中でほ乳びんにすり替えると、抵抗なく飲むことがあります。赤ちゃんがウトウトしているときや空腹時に成功しやすい方法です。また、おもちゃで気をそらしてすり替える方法もあるでしょう。何度もすり替えを行ううちに、ほ乳びんに慣れて、次第に嫌がらなくなるケースがあります。
【対処法4】ほ乳びんの乳首を温める
ママの乳首に慣れていて、ほ乳びんの冷たい飲み口を嫌がっている場合があるため、ミルクをあげる前に乳首を温めてあげる方法もおすすめです。お湯に浸してみたりほ乳びんを傾けてミルクで温めたりしてから飲ませてみましょう。寒い季節には特に効果があるかもしれません。
【対処法5】乳首の先に母乳をつける
ほ乳びんの乳首を含ませる前に、乳首の先に母乳をつけてあげると、赤ちゃんが勘違いして飲み始めるケースがあります。母乳の味に安心するのも大きな理由かもしれません。母乳メインの赤ちゃんがほ乳びんの練習をする際は、粉ミルクではなく搾乳を与えることから始めるのも効果的です。ママの匂いがする母乳は、赤ちゃんが安心します。
【対処法6】ほ乳びんの洗浄方法を変える
ほ乳びんの洗浄時についたにおいが気になって飲むのを嫌がっているケースがあります。ほ乳びんを洗う際に使う洗剤を変えてみるとよいでしょう。たとえばアラウ.ベビーの「泡ほ乳びん食器洗い」は合成香料、着色料、保存料は一切無添加で、洗浄力に優れ、泡切れもよい商品です。
消毒方法については、薬液消毒から煮沸消毒、電子レンジ消毒に変えてみましょう。
<ほ乳びんの洗い方と消毒方法について知りたい方はこちらの記事をチェック!>
→ほ乳びんの洗い方と消毒方法|赤ちゃんのために清潔な状態をキープ!
【対処法7】ほ乳びん以外のもので飲ませる
生後2か月くらいであれば、コップやスプーンでミルクを飲ませてみる方法もあります。コップやスプーンの利用は、清潔なほ乳びんが手に入らない災害時などでも有効な方法です。シリンジ (注射器の筒)やスポイトを使う方法もあります。また、生後4か月くらいならスパウトマグ、生後8か月くらいならストローマグも試してみましょう。
生後8か月をこえるなら、早めの卒乳の可能性もあります。離乳食でしっかり栄養が摂れるようになると、ほ乳びんでミルクを飲むのを嫌がる赤ちゃんもいるのです。主治医の先生に相談してみましょう。
焦り過ぎないことも大切!気持ちに余裕をもって試行錯誤を
ほ乳びん拒否は、よくあるママの悩みの一つです。
体重増加の不足や保育園、ママの体調面睡眠不足や疲労など、ほ乳びんが必要なの理由があるのに、赤ちゃんがほ乳びんでミルクを飲んでくれないと、「ほ乳びん拒否はいつ治るの!?」などと焦る気持ちが高まるでしょう。すると、ママ・パパの気持ちが伝わり、赤ちゃんが不安になって、ますますほ乳びんを嫌がる悪循環が生じやすくなるようです。
心配のあまり小児科医や助産師に相談したところ、「お腹がすごく空けば、嫌がっていられずにほ乳びんから飲むから大丈夫」と言われたケースもあります。確かに赤ちゃんも生き物です。空腹感が強くなれば嫌がっていられなくなるかもしれません。
「拒否」という言葉からネガティブなイメージをもってしまいがちですが、「赤ちゃんはママのおっぱいが大好き」とポジティブにとらえて向き合うとよいでしょう。
ほ乳びんが使えなくても慣らし保育を受け入れてくれる保育園もあります。ベテランの保育士がコップやスプーン、シリンジなどさまざまな方法で練習してくれるでしょう。保育士が与えてみたらほ乳びんから飲んだというケースもあるようです。
大切なのは気持ちに余裕をもって赤ちゃんに合う方法を見つけること。時には気分転換もはかりながらリラックスして記事で紹介した克服法を試してみてください。